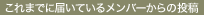

勝手に基準をつけないで(chobi)
個性とかの問題より、勝手に基準つけて、その他の能力をもっている子はどうすりゃいいの?

競争しないことが平等?(プッチりんご・広島・33歳)
わたしが小学生の時から「対抗」とか「競争」という言葉がタブーになり始めていました。わたしは足が遅く、徒競走やリレーがイヤでした。でも絵を書くのとモノを作ることが大好きで、そちらの評価は高くなり、ますます好きになったものです。優るものを正当に評価してもらえれば、劣の部分を気にしないでいられました。今の教育は、子どもの能力の優劣を認めることもしないのでしょうか?

なぜできないのかも見てほしい(なほ)
「運動は苦手」がわたしのコンプレックスでした。それを教師が「早い子はいい」、「跳び箱は、高い段を飛べる子がすばらしい」という目で見ていた、その事実がイヤでした。「みんなを同じレベルに」という努力はある意味買いますが、苦手なことも、得意なことも伸ばせるように、子どもの個性をもっと磨いてほしい。自分の子にはそう接していきたい。そのためには、少人数のクラス作りをお願いしたい。
評価のみではなく心のフォローまでが責任(Donuts・既婚・30歳)
みんなが同じ才能をもっているわけではなく、分野ごとに優劣がついてしまうのもごく自然なこと。大人は、単に優劣の結果だけをふりかざすのではなく、劣ってしまった子には「たまたま、この分野で劣っていただけ」ということを、しっかりと伝えて励まし、優れた子には努力や才能を認めてほめて伸ばす、といった心のフォローをする責任があると思います。
達成度の早い遅いで傷つけないで(フレーバーママ)
子どもの小学校では、足の早い子から順に組を作り、徒競走をしました。達成度に合わせて、正々堂々良い戦いをしたと思います。でも、もし、トップの子どもの中に、一人遅い子が混じったら、大変なダメージを受けてしまうと思う。イジメのように。時間さえかければ誰もができるようなことの、達成状況の遅い、早いといった程度の差で、子どもたちの心に大きな傷をつけたくはないと思います。
劣等感を助長することも(ななこ)
わたしは運動がとても苦手だったため、運動会やマラソン大会は大嫌いでした。親や友だちがたくさん見ている前で、最後にゴールすることのみじめさを何度も味わってきました。勉強などの成績は、多勢の前で公表されることはあまりないのですが、運動はそうではありません。評価そのものは否定しませんが、習熟度別クラスなど、はためにはっきりわかるようなものはどうかな、と思います。
子どもの気持ちになって!(sayuki)
学生です。優劣をつけられる側になってみてください。優れていると評価されるのは嫌ではありませんが、時には重荷となることもあるはず。周りの人に、「優れている人」と常に思われているのは、その人にとってはいい迷惑です。反対に劣っていると評価されたら、自分を卑下して、悪いほうに考えていくのではないでしょうか。評価することは大切だとは思います。評価方法の工夫が必要です。
先生の平等意識の欠落(tazu)
わたし自身、日本の学校ではあまり成績が良いほうではなく、先生たちも成績のいい生徒をかわいがる傾向にあり、それがとても悲しかった思い出があります。アメリカでは、できないことを悪いとはせずに、それを生徒同士が助け合っていました。その子のもつ良いところを見い出してあげるのが「指導する」ということ。先生の、子どもたちに対する平等の目が、日本では欠けているように思うのです。
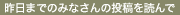
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
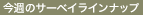
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録