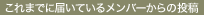

世界を広げるきっかけになる(文月・栃木県・既婚・37歳)
ボランティア活動は、興味があってもはじめるきっかけを見つけるのが、なかなか難しいのではないかと思います。特に中学、高校時代は。だから、たとえ強制的とはいえ、とにかく体験してみる機会を得ることは、よいことではないかと思います。大切なのは、ただやりっぱなしにするのではなく、お互いの体験をクラスで発表しあうとか、福祉にまつわる問題点などを一緒に学んでみるとか、点数としての評価をするだけで終わらせないことではないかと思います。ボランティアの授業は、ひとりひとりの世界を広げるきっかけになると思います。
自分の道を模索するためにも(jullia)
子どもたちにいろいろな経験をさせてやりたい。その中から自分の道を模索していってほしい。そう考えると、親が体験させられることには限界があります。学校でボランティア体験をさせてもらえるのは、親の立場ではありがたいことです。きっかけはどんな形でも、多くの子どもたちがボランティアの現場を経験することは大切だと思いたいです。

教師も指導の仕方に工夫を(ルッコラ)
ボランティアって本人の気持ちが一番大事だと思うんです。強制的にボランティアに参加させられて、相手にもいやな思いをさせることになるんじゃないかな。指導の仕方を教師も工夫しないと、ただの押し付け、その場しのぎ、得るものがなにもない、そんなことになってしまうでしょう。だいたい、今の教師にボランティア精神ってあるんでしょうか?
「有志」の意義がなくなります(Kikumi・アメリカ・既婚・37歳)
「有志」である、ということがボランティアの第一義であるはずなのに、授業で、しかも評価の対象なるシステムになると、「有志」の意義がまったくなくなりますよね。最近では、ボランティアに出かけて交通費をもらうとかおこづかい程度の報酬をもらうこともあると聞きます。わたしがするボランティアは、交通費を払ったり自腹を切ることがあっても、「させていただく」というものに限っています。自分がしたい! と思ってさせていただいていることに見返りを求める癖をつけることに危惧を覚えます。成績や人格、社会性の向上をおおっぴらに「やっているのよ」と見せることによる素人のパフォーマンスにならぬよう、ボランティアを受ける側の気持ちを真っ先に考えられる誠意があってほしいと思います。

方法論を子どもたちに教えて(babuakira)
ボランティアを「教育」として教え、それを成績として評価するのはいかがなものかと思います。ただ、ボランティアとの関わり方などを教えることはよいことだと思います。昨年、わたしも初めてボランティア体験をしたのですが、今まで、ボランティアをしようとは思いませんでした。ですが、さまざまな形でのボランティアもあるんだということをその体験で理解できたので、そういう方法論を子どもにも教えていくべきではないかと思います。ボランティアは他人に対して満足を与えるためのものではなく、自己啓発のためにするものだとわたしもそこで学びましたから。
入り口を提供してくれる(DORI)
「ボランティア」が評価対象になるのは反対です。でも、そういう「ボランティア」への糸口が分からない親・子どもにとってその入り口に立つという意味ではそういう体験を学校側が提供してくれることはいいのではないでしょうか。
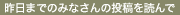
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
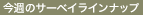
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録