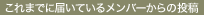

生卵も心配(元おやじギャル・パートナー有・39歳)
牛肉に関してはカレーのルウなど、ビーフエキスの入ったものは信用できなくなりました。また、生卵の危険性が報じられていないのを危惧しています。以前香港で鳥のウイルスが発生した時、米国では肉のことよりも、卵の殻を介して生卵が体内に入ることを警告し、生卵を食べることを禁止していました。
肉風味の「なんちゃって肉料理」(ROSAY・東京・パートナー有・27歳)
わが家では、以前から魚中心の食卓です。月に数回の肉料理を作るのですが、やはり、ニュースを聞くと肉や卵を買うことができません。とはいえ、たまに登場する肉料理が楽しみな主人にとっては、ショッキングな出来事のようで、食感だけでも、肉風味の「なんちゃって肉料理」をいわしのはんぺんや切干大根で作っています。味付けを似せると肉風味です。
普段は販売側だけれど(愛食家・千葉・パートナー無・27歳)
わたしは某食品スーパーマーケットに勤めていますが、これは消費者にとっても、販売側にとっても大問題ですよね。自分が仕入・販売をする側としての知識や情報を持っていても、いざ消費者の側になると、やはり鶏肉を買うことには躊躇してしまいます。鳥インフルエンザが発生してからしばらく様子を見ていたという生産者に対しては、「安全」に対する気持ちが欠如していたとしか考えられません。
食肉の問題を起点に考え直したい(アミー・東京・パートナー無・49歳)
さらに韓国で新たに豚コレラが発生したということを耳にしました。これで主だった食肉が全滅ですね。これらの問題は食について根本から考え直すためのひとつの警告なのではないかと感じています。地球上に餓えている人たちがいる一方で、食べ物を残し罪悪感を抱くことなく平気で捨てている人たちもいる。家畜に対しても生き物というより単なる「物」くらいにしかとらえていないよう。
人間が生きるということが、牛や鳥などの命の犠牲の上に成り立っているということを今こそ真摯に受け止め、食に対して思いを改め、無駄をなくしていくことがまず大切なのではと思われます。また商業ベースに乗せられた家畜は抗生物質入りの配合飼料を食べ薬漬けになっています。それを人間が食べています。家畜に限らず野菜も農薬や化学肥料を使っており、土壌や河川そして海までをも汚染しています。「食」の問題はまさに環境問題につながります。今回の食肉の問題を起点として、「食べ物を大事にする」「健康を考える」「環境問題全般に関心を持つ」など多くのことに考えをめぐらすことが肝要なのではないでしょうか。
米国政府のコメントに購買意欲をなくす(月夜桜・兵庫・パートナー無・29歳)
昨日家族で家の前のフォルクスに行ったのですが、アメリカンビーフは避けてしまいました。買い物でももちろんそうです。今は生卵を買うのも不安です。鳥肉は国産のいいものでも食べる時に、「大丈夫かな」と思ってしまうので、楽しんで味わうことができません。生産者・流通業者・国などが「安全ですから大丈夫」という言葉を信じきれなくなったのはいつからでしょうか。牛肉に関してのニュースで、米国政府のコメントを見ると、「売れないと困るから無理をしてでも売ろうとしている」と感じてしまい、ますます購買意欲がそがれてしまいます。
しばらく控えるくらいで大丈夫?(ごまたま・千葉・パートナー有・30代後半)
牛肉はあまり食べないのでほとんど影響ありませんが、鳥肉は問題。わが家では、肉といえば、鳥というほど大好物で、ほかの肉はめったに食べません。でも鳥インフルエンザって2、3年前に香港でもはやったし、昨年末は韓国でも流行ったし、今年は山口県とベトナムで発生しているんですよね。はやっている時期だけ、しばらく食べるのを控えるくらいで大丈夫かもしれないと思っています。

「なんか気持ち悪い」という感情(aim↑・山口・29歳)
人の病気にしても食肉にしても、「かかる人はかかる、かからない人はかからない」の自論で購買に変化はないので、そこまで過剰反応して神経質にならなくても、と常々思っています。しかし、自宅と直線50キロメートルという目と鼻の先で起こった鳥インフルエンザには、さすがに動揺しました。次々と卵が回収され、店では撤去と返金対応、対策本部の設置に、鶏3万4000羽埋却、という混乱ぶりです。牛肉に続き、鶏卵・鶏肉の購買が落ち、便乗値上げがあり、株価にも影響だなんて、どうなってるの?と疑問に思いつつもこれが現状です。正しい報道がなされていても、「なんか気持ち悪い」という感情はなかなか拭えないのでしょう。
もはやどれも安全といえない(さーぼー・東京・パートナー有・31歳)
食の安全にかかわる報道があっても、たとえば牛肉を買い控えたり鶏肉や卵を食べないようにしたりということはありません。産地がどこであろうが、「これは安全!」と言い切れる商品は、もはやありません。
一連の報道は、消費者が商品をたしかめる目と判断力を持ついい機会だと思います。畜産家による毎日の血のにじむような努力のもとに、わたしたちは食にありつくことができるわけですが、生産コスト抑制のために手段を選ばず、過剰な供給を試みた結果が今日の食に対する不安を招いているのも事実です。家畜を単なる商売道具としか見ていない粗悪な業者は淘汰されるべきではないでしょうか。そしてわたしたちは、尊い命に生かしてもらっているのだということを忘れてはならないと思います。
安全な牛肉を輸出せよ、と要求すべき?(こうむ・神奈川・パートナー有・45歳)
今まで、材料として購入する時は、国産のもののみを選んでいたので、とくに影響はなありません。外食・中食時には影響があるかもしれませんが。今回の米国の牛のBSEの問題の中で驚いたのが、外食産業が「輸入解禁」ばかりを要求していることです。まず何よりも、「安全な牛肉を輸出せよ」と米国に要求すべきだと思うのですが。
また、某新聞には、農水省が検査費用の一定の割合で日本側が負担することを提案しようとしている、とありました。その後、この検査費用負担について報道がないので、実際のことはわかりませんが、米国がすべきことを日本がする必要はまったくなく、税金の無駄遣いだと思いました。わたしたちも、安いだけではなく、安全にも気を使って、食を選択するべきだと思います。
何が危険で、何が安全か(norico9110・神奈川・パートナー有・32歳)
実際の食生活での変化はありません。どちらかというと、消費者である自分の意識以上に、敏感にす早く売場の方が変わったもしれません。何が危険で、何が安全か。真偽をよく理解しないまま、言われるがままに「牛は危険、鳥も危険」と流通も消費者も騒いでしまっているように見えます。本当に危険な食品はもっとあるのでは、と思えてなりません。
むしろ農薬やブロイラーのほうが(miyaco・兵庫・パートナー有・29歳)
生産者限定の肉屋さんや生協など、心意気のあるお店を普段から利用しているので、とくに心配はしていません。「この店ので駄目だったら、いまごろ日本中大パニックだろう」ぐらいの気持ちです。外食のときは少し気になりますが。でもBSEや鳥インフルエンザより、農薬やブロイラーなど恒常的なもののほうが怖いです。
お店の情報を信用しようと思い(イクラ・東京・パートナー無・41歳)
ここ何年か食品に関する問題が続出していて、もしかしたら、これって今まで表沙汰にならなかっただけで、昔からあったのでは?と、疑いたくなる心境です。そもそも生産者と消費者は信頼関係がなければいけないはずなのに、崩れている気がします。個人が原料の安全性まで把握するのは、今の流通状態ではなかなか難しそうですし、究極的に考えれば野菜は自分で育てることもできますが、肉に関してはまさか牛を飼うわけにもいきません。
今、わたしはお店の情報を信用しよう!と思って食材を買い、お肉に関しても、とくに控える種類はありません。こういう消費者がいることを生産者・流通関係・関係省庁に知ってほしいし、大げさに言えば、命懸けであることを考えてほしいです。
自分の判断が頼り(春菜・埼玉・パートナー無・31歳)
もともとほとんど食べないので影響はありませんが、鶏・牛問題に限らず食品の安全性に関して、結局は自身の信念に基づいて総合的に判断するしかないと思います。表示などによって与えられた情報に対する信頼性の線引きをどこでするかを自分で決めたら、それを信じるのみです。それが正しくできるように、知識と判断力を持ちたいと思います。
人間、いつどこで死ぬかわかりません(コジまま・富山・パートナー有・38歳)
明日、交通事故で死ぬかもしれません。そうなれば、毎日、おいしい物を食べたいです。もちろん、食品を買うときは、情報が入る限り、農薬や生産地など把握しながら、生協を利用したり、スーパーなどのチラシなどよく見ています。
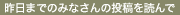
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
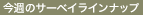
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録