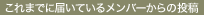

子どものスピードに合った指導を(mamarin)
非常に難しい問題ですね。まず自分の子どもについて。長男(新5年生)は理解するまでに時間がかかるのですがいったん理解すると応用できるタイプです。ですから時間をかけてやればいいのですが、とりあえずこれを覚えなさい、覚えなければ次へ進めないというような項目を教えるのに苦労します。長女(新3年生)は逆にすぐになんでもとりあえず記憶し、先生の言うことを一言も漏れなく聞いているので、今まで学習に関して悩んだことがありません。
それから現在2歳から13歳までの子どもに英語を教えている教師の立場から言えば、本当に子どもの学びのスピードは千差万別で、能力もそれぞれすばらしいところがあると実感していますので、一人ひとりに覚えやすいように教える努力はしています。でも保護者の方は、やはりほかのお子さんと比較して不安になられているようです。親としてそれもわかるし、難しいです。
小学生の宿題の量が心配(巨人の星・静岡・パートナー有・41歳)
自分も勉強が嫌いで、勉強はしなかったので、必要以上の勉強は必要ないと思いますが、今の小学生の宿題はとても少なくなっていて、親としても心配になります。

興味のあることを自主的に学ぶ姿勢を(ocarina・東京・パートナー有・38歳)
以前どこかで読んだものに、「教育」とは、子どもの持って生まれた教えを育てることだとありました。本人が「教え」を持っているならば、大人は、それを上手に見守ることが最重要。学校の勉強にはついていってほしいけど、それ以外では、興味のあることを自主的に学ぶ姿勢をもってくるといいと思います。
教育改革にもっと力を入れてほしい(お気楽みわちゃん・岐阜・パートナー有・38歳)
入学前までは、早かろうが、遅かろうが、あまり親としても考えずに過ぎてくるが、学校という組織の中に入り、小学校高学年、中学となってくると、あ然とすることになる。私見としては、各々の能力の差があるのは、一人ひとりの顔や指紋が違うのと同様に、個性なのだから、認めてやりたいと思う。でも、まずは教育改革にもっと力を入れてほしい。人材も予算も。
兄弟のスピードの違いにびっくり(すばらしい!・千葉・パートナー有・41歳)
わが子が小学校に入ったとき「いくつといくつ」という単元で二人ともつまづきました。「5は3といくつ?」という問題で、上の子にはおはじきで説明してもわからず、図で書いたり、おやつを使ったり、2時間も悪戦苦闘。理解力の低さにぼう然としました。案の定「お」と「を」の区別が3年生までつかなかったり、テストも100点はほとんどとったことがありませんでした。
ところが、下の子は「5は3といくつ?」をおはじきで説明したところ、即座に「5ー3とおんなじだね」「まだ引き算は習ってないよね。2つに分けるから引き算とはちょっと違うんだよ」と言っても「でも5から3をとるのと一緒だから、引き算でできるよ」と反論。結局1分もしないうちに解けるようになりました。
テストも100点が多く、なぜ兄弟でこんなに違うのかとびっくりです。1年入学の時点で能力差がこんなにあるのかということに、親になって初めて気付きました。しかし、できない兄は努力家。まじめにコツコツと勉強するので、高学年になってから、グーンと伸びてきました。男の子って急に伸びる時期がありますよね。成長のペースって一人ひとり違うのだな、と感じています。
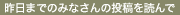
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
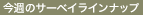
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録