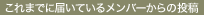

親として環境を整えられる機会(mame・東京・既婚・35歳)
わたし自身がわ私立校へ通わせてもらっていたので、自分が受けた教育がよいと考える部分が多く、子どもも私立校に通わせようと思っています。親が環境を整えて与えてあげられるのは、人生の中でもわずかなチャンスだと思います。成長していくにしたがって、選択していくのは本人なので、そこで公立校を選択してもよし。そのまま、また私立を選択するもよし。その時々で相談相手になることを心がけて……。最初の教育環境は、私立校へと考えます。
教育方針を明確に(ぷにまる)
わたしは中学受験を経験して、中高一貫の学校で思春期を過ごしました。公立校の教育が問われる現在、人間人格の育成に大事な時期を、受験勉強にとらわれることなく過ごすことは、とても貴重だと思います。ただし、自分の子どもに、どのような教育を受けさせたいかを明確にすることと、私立校といっても個性はいろいろですから、その辺をよく見極めることが大切だと思います。公立校と私立校というだけで分けて考えてしまっては危険だと思います。
教育だけは、不自由なく受けさせたい(Hiromi)
離婚して、ひとりで子どもを育てていますが、それを子どもが十分に教育を受けられない理由にしたくありません。現在息子は6年生、受験勉強の真っ只中。私立中学校の説明会に出向いて思うのは、勉強はもちろん、学校生活全体で子どもがどうしたら伸びていってくれるのかについて、各校真剣に取り組んでいること。公立学校でここまでケアしてくれるのだろうか。大学は国立に入ってもらう(もう決めてる)ので、学力をそこまで持ってってくれるのは、私立校だと思っています。

受験期を通りすぎればただの人(Maja)
「三つ子の魂百まで」と言いますけれど、結局はDNAと個性の問題だという感想です。かつてはお受験のための家庭教師もしたり、わが子の偏差値に一喜一憂したこともありました。でも、大学生の学力低下や、理科系離れ。資格はあるけれど使えない若者を見ていると感じるのですが、環境を整えてあげても自発的な研究者にはなれないということです。学歴も肩書きも資格も、ないよりは便利だと思いますが……。
親の意識を変えることも必要かも(コリエコリコ・既婚・40代)
わたし自身は私立校一筋で、自分としては満足していますが、それがすべてでないとも思っています。息子たちはまだ幼稚園、現在海外で、ちょうど小学校入学時に帰国予定なので、お受験は望めません。公立校でもいいと思っていますが、いろいろ聞くと不安な面も。ただ、海外の学校で思うのは、親が学校に深く関わって、積極的に参加しているということ。公立校でも学校を変える道はあるのでは、と考えさせられています。

個性的な授業を受けていました(maiK)
わたしは中・高の6年間を、某国立大学付属校で過ごしました。通常の授業のレベルが高かったか低かったかはわかりませんが、教育実験校のような位置付けだったため、今思えばおもしろい試みが多かったと思います。たとえば、高1の時に数学の論文を書かされたり、いろいろな考えを持った先生の公民の授業があったり。実験されている中で、学生は環境や情報を自分で取捨選択していくようになるわけですが、「影響を受ける」きっかけが多い、しかも個性的な影響源が多かったのは確かですね。
地域にもよるのでは?(nanachin)
わたし自身の体験ですが、わたしは高校1年生まで富山県で過ごし、高校2年生になる時に横浜に転校してきました。どちらの学校も県立校で、その学区では一番レベルの高い(偏差値の高い)学校でしたが、その内容の差は歴然としたものがありました。富山の学校では、塾なんて行く暇がないほど大変熱心な教育がなされて、わたしたち(生徒)もそれについていくのに精一杯。生徒一人一人の志望校やテストの答案(どのような間違いをしたか)を、先生がすべて把握していました。一方、横浜の学校に転校してきたら、先生は教科書の内容をなぞるだけ、受験対策は全くしてはくれず、むしろ「塾へ行ってください」と保護者会で説明される始末……。そのギャップには正直びっくりしました。しかし、だからといって富山の教育がいいというわけではなく、高校といいながら受験のための予備校化している面もあったのは否めません。
私学、公立でも同じ(いまいくん・埼玉・既婚・39歳)
大学で同じ研究室だった同級生が、私立高校で教師をしていますが、彼の話を聞くと私立校でも「問題教師」はいるみたいです。どう考えても教師としての適性が無いのに「落ち度」が無いためクビにもできず、そのまま居座っているそうです。こうなると転勤のない私立校の場合、かえってたちが悪いかもしれませんね。そのわたしの同級生、研究室の中で一番成績が悪かったのですが(笑)。でも今ではちゃんと先生らしくなって、その学生時代からのギャップには驚かされます。先生の適正は、学校の成績だけじゃないってことですね。
受験させたいけれど(たれまま)
文部科学省の「ゆとり教育」報道以来、子どもを公立校に通わせることに、急に不安を覚えています。自分は公立校育ちなので、公立校が悪いとは一律には言えない、と思っているのですが、こう方針が定まらない状況だと、教育現場は混乱してるだろうなということは容易に想像つくし……。私立校は、方針さえあえば、いろんな選択肢があると思うわけです。でも、ワーキングマザーにとっては、保育園(そのうち学童も)を通じ、地元の良さ、ありがたさも身にしみていて、地縁の薄い私立校には、通わせるのは大変かなあと。保育園の毎日の送り迎えに夫婦で四苦八苦している現状で、この上受験準備なんて、至難の技。最近は受験に挑戦されるワーキングマザーが増えていると聞きますが、よほどの意志がないと続かないと思います。学費の高さもやはり気になりますし。親子ともども無理せず、子どもがのびのびできる環境を、どうやって整えていくか。今後どうしていこうか、今まさに悩みどころですが、子どもの性質に合わせて、その時のベストチョイスができればと思っています。
公立は頼りにならないけれど……(rainyblue・神奈川・既婚・40代)
息子が公立校の中学の3年生です。塾へ行き始めたら「今まで学校で習っていたことより、わかりやすくておもしろい」と言っています。「学校はいらない、塾だけで勉強したい」とも。公立校の先生のすべてがそうだとは言いませんが、教える技術がなさすぎます。「ここは塾で習うだろうから」と飛ばしてしたり、論理的ではないので、生徒が混乱してしまったり……。教えるというプロ意識に欠けている先生が多すぎるというのが、公立校の現状です。ただ、だから私立へ行けばいい、という問題ではないと思います。経済的に余裕のない人は、公立でいい加減な授業を受けるしかない、というのは間違っていると思います。
親の役割って何だろう?(takachan1021)
二卵性双生児の息子たちは、今、中学3年生です。受験は、子どもたちにとっての大切な人生の節目で、大事なのは「私学か公立か」ではなくて、等身大の子ども自身を知るために意義のある節目だと思います。親に行かされるのではなくて、子どもは自分をとりまく環境を理解し、自分で選ぶことが大切です。家庭の中の経済状態を知ったり、奨学金制度について学んだり、親子のコミュニケーションが深まるいい機会だと思います。報道が一人歩きして、ともすれば、低学力だとか、受験の結果だけでの人との差別化にまどわされているように感じます。終身雇用の神話が崩れ、日本の企業の体力が衰退し、文部科学省で働く人たちも学校の先生も、迷路をさまよっているのが現状でしょう。いっそのこと教育も民営化すれば、日本も変わるでしょうか。
わが家の息子たちは、こつこつ夏休み中、一日8時間以上勉強していた次男は私学へ、8月になって塾を辞め、所属していた陸上部の練習に励みだした長男は、公立校へ進学を希望しています。それぞれ自分が行きたい理由があります。わたしができることは、エールを送ることだけ。わたしは常々自己決定できる力が大切だと思い、子どもを一人の人間としてつきあってきました。わたしが大切にしたいと思ってきたことが、受験という節目を前にして、彼らに根づいていることをうれしく思います。「通るのも人生なら落ちるのも人生、結果は後からついてくるものよ」。そんな会話を、今日は子どもとしました。
子どものためと言いつつ(弓ちゃん・既婚)
以前は受験を考えていました。近くに私立の小学校があったからですが、なぜ受験させるのかと改めて考えた時、子どもの可能性の道を広げるためとか、いい進学ができるためとか、子どもにプラスになることが多いと思いつつも、親の見栄の部分があったことも確かです。「すごいわね」と言われたい自分が、なかったとは言えません。その学校のこともよく知らないまま受験を考えたことが恥ずかしい。結局、夫の実家のある土地に引越し、受験をさせても、電車通学はしのびなく、公立の小学校に通っていますが、これでよかったと思っています。
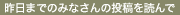
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
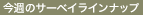
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録