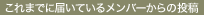

教育改革を外国に倣ってもいいのでは(けい)
あまり安易に外国の育児や教育に倣うということは嫌いですが、これに関しては欧米に倣ってもいいのではと思います。週5日しか行かなくても、有能な人材はちゃんと育っていますよね。少し古いですが、子どもたちの休みの日は住んでる地域でスポーツをしたり、親の離婚で一緒に住んでいない親の家に行ったり、ガールスカウトの集まりに行ったり、また有名プレップスクールの子でも、自分のつくったアクセサリーを売っていたり(これは大きな勉強になると思いますよ! )、健康的で「生きる力」を養っていると思いますよ。日本は今まで週6日学校に行っても東大が世界で30位ぐらいのランクにいるんじゃ、小学校から大学まで教育の根底から改革しないと話にならない。ゆとりって何なのでしょうか。学問はきっちり学問として教えてほしい。ただ、ついていけない子のために、セカンドチャンスや再起復活戦などのオプションを用意する。がんばってもできない子については、勉強ができなくても誇り高い人生があることを学校でも教えればいいのではないでしょうか。
選択の余地という「ゆとり」が生まれます(奥沢すずめ)
子どもが学校に上がって初めてわかること。ゴールデンウィーク以外、気候の良い時には旅行も何もできない。好むと好まざるに関わらず民族の大移動に加わざるをえないこと。サラリーマンには有給休暇があっても子どもにはないのです。毎週連休があれば家族のレジャーも広がります。勉強にしたってそうです。すべての子どもに合う教育などできっこないのです。学校教育の標準を高めてできない子の「お客さん」を増やすか、低くしてできる子にお客さんになってもらうか。より多くの人の選択の余地を考えると後者でしょう。できる子は塾に行く、参考書で自習する、いろいろな選択肢があります。

もう一ヶ月以上経ったのに、まだ「レッスン1」(binko)
今、下の子どもが中1です。今年の1年生の中間テストの科目が、国・社・数の3科目だけです。え! と驚きました。そして、テスト前だというのにゲームばっかりして、学校は本当の勉強を教えていないように思えてならない。それに、もう一ヶ月以上になるのに、英語は、やっとアルファベットを書かせて、まだレッスン1だそうです。何を教えているのでしょうか……と思えて、学校に任せられない気持ちです。ゆとり教育は、子どもを怠け者に育てていくように思えてならない。
少人数制の落とし穴(いまいくん・埼玉・既婚・39歳)
少人数学級を進めるべきとのご意見がありましたが、「はずれの先生」に当たった時には少人数で教師と接する密度が濃い分、子どもへの悪影響が大きいのではないでしょうか。教師という職業は、真剣に取り組めばこれほど大変な職業はありませんが、手を抜こうと思えばいくらでも手を抜けます。高校の教員をしている友人が「誰が見ても教員としての素養のない教師でも、辞めさせることができない現状の制度は問題だ」と言ってましたが、こんな「はずれ教師」がいたら、ゆとり教育も少人数学級も、まるで意味がないでしょう。何よりも教員の質の底上げこそが急務です。
学校の意味を問い直すべき(智子・未婚・25歳)
「教育」と言いながら学校に通う時間を減らすことにまず素朴な矛盾を感じます。学校とは集団生活と勉強を学ぶ場です(土曜休みで削減されつつある学芸会や運動会も、子どもにとっては大切な出来事であり、学ぶ場です)。政府はこれを「ゆとり」という名目で放棄したとしか思えません。学校という大切な場所を、本来の目的達成のために正常化することが先決ではないでしょうか。
「新学習指導要領」に疑問(づみ)
週2日制より「新学習指導要領」に疑問を感じます。学習内容を変更し、減らして、なにがゆとり教育なのでしょうか? 小さい時ほど吸収力があり、なんでも覚えられる世代。その時期に減らしてしまっては意味がないと思います。また、小学校でパソコンを授業に取り入れる必要があるのでしょうか? 基本ができていればパソコンも問題なく操作できると思うし、ゲーム世代の子どもたちには問題だと思っています。それに、20年前より確実にだれでも使えるパソコンになってきています。それより、基本的な算数、国語、英語、そのほうが大事だと思います。

先生は、かえって忙しくなったとか(Maja)
高校の先生の感想は、土曜日に部活や補習の予定がびっしりと入って、かえって忙しくなったということです。子どもたちが自発的な学習や地域活動に参加ができるようになるまでには、かなりの準備期間とお膳立てがないと戸惑うばかりです。指示待ちの子どもが増えている現状では、日ごろの家庭や地域の教育力が問われている。すぐに結果の出るものではないので、しばらくは様子を見ていようと思います。これからは地域格差、学校格差が広がるのでしょうね。
ドイツでは二極化が進んでいるようです(klang)
ドイツでは、日本の小学校にあたる学年では、子どもたちは平日も早々に授業が終わります。朝始まる時間は早く、休み時間は教室の移動で精一杯な程度に短いから、それが可能だとか。低学年では、14時には家に戻ってくるような感じです。もちろん週5日授業。共働き夫婦も多いし、教育熱心ではない家庭の子どもたちは、不良化する場合も少なくないと聞きます。というわけで、既にドイツでは、「二極化」した子どもたちの実態が、以前日本でも話題となっていたPISA(OECD生徒の学習到達度調査)でも顕著となりました。日本の今後も、心配ですね。
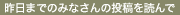
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
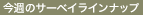
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録