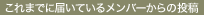

わが家はゆとり派(jks)
朝7時ちょいすぎに登校し、帰りは3年生で3時半〜4時、遊ぶ時間は1時間ちょっとといううちの子たちにとっては、そして親にとっても、2日間の休みというのはありがたいものです! どっちかの日に、普段しない片付け、上履き洗いなど、自分のことは自分でするという習慣付けになり、そこは田舎の強み? か勉強勉強とならんでもいいこともあり、今のところ問題ありません。今後のことはどうするつもり? という声が聞こえてきそうですが、男の子は今の時代、したいことがなかなか見つからないと本に書いてあるぐらいなので、それを見つけるのにも、2日間の休みと言うのは有効かもしれないと思っています。
親が試されると思います(ぼよん)
うちの父はずっと週休2日だったし、自分も大学からは週休2日がアタリマエの状況だったから、週休2日はゆとりがあるなぁと素直に思っています。娘は5歳、最近のわが家族の週末は、土曜日は車でおでかけ、日曜日は近場の公園に行ったり、美術館に行ったり、図書館に行ったり、商店街をぶらぶらして、夕食は家族で餃子やうどん、ピザなどをこねこねして作るのが日課になっています。共働きなので、2日間の休みは貴重です。子どもといかに面白く過ごせるかを、夫婦で平日にいっぱい考えています。わたしが考えるゆとり教育って「実体験」なんです。ゆとりがない場合、「せみは甘い蜜が好きです」なんて字や絵で解説されたものを知識として習得します。ゆとり教育は、実際に甘い蜜をつくって木に塗ったり、せみの鳴き声を聴いたり、体験に基づいた知識として習得できます。都会っ子の娘には、実体験が少なすぎるのです。だから、いかに実体験をさせるか、大人になるまでにいっぱい体験させたい、その思いが強いです。そのためには週休2日はアタリマエだと思うし、親も努力しなくちゃ。目で勉強するんじゃなくて体全体で学んでほしいから、わたしたち夫婦は、あーだこーだと子どもと一緒になって日々考えています。とにかく、本当は毎日遊んでいたい。でも、親がネタギレになっちゃうかもしれない……(笑)。

「ゆとり」って教育することなのか?(hamaiso)
数年前、M省のお偉方を連れて某県の理科教師の勉強会に行ったことがあった。それは、学校週5日制に伴う学習指導要領の改正についての講演だったのだが、参加者の先生方は「小中学校で身につけるべき基礎力をつけず、高校で実験ばかりやらせても理解できているとは言い難い」「進学する子だけではなく、社会に出る子にも教養としての理科を身につけさせたいのにそれができない」等々、なかなか現実的な意見が出ていた。それに対するお偉方の答えは「それ以上のことを勉強したければ、自由選択科目で取らせりゃいいだろう」「今までの学習指導要領だって、基礎力が身についたかといえばそうではない」「わたしが考えた新指導要領ではないから知らない」等々の無責任な発言のオンパレードで、随行していたこちらが恥ずかしくなるほどだった。「ゆとり、ゆとり」と喧伝しているが、「ゆとり」の感じ方は人それぞれ。自分で作り出すものであり、人から教育される類いのものではない。このような状況の中で、受験制度は変わらないわけだから、逆に「教育貧富」のような格差が出てくるのは必至だろう。
できる子とできない子の二極化(けろろん・北海道・既婚・33歳)
学校の先生に聞いたところ、ゆとり教育の導入で、生徒の層が勉強ができる子とできない子の二極化が進んだとのこと。以前は学力が中間層の子が大部分を占めたのに、ゆとり教育の導入で、意識のある親は塾などに通わせ、意識のない親はそのままにしており、学校のレベルが下がるにつれ、どんどん子どもの学力も下がっているとのこと。従来なら、塾へ行かなくても学校の勉強+アルファぐらいで結構いい成績を修められた子もたくさんいたのに、ゆとり教育の導入により、結局は親にお金があって塾に通わせられる子だけが学力をつけるということになりかねません。子どもたちが学力をつけるチャンスを奪ってはいけないと思います。「ゆとり」とは自分で生み出すもの。ふだん一生懸命に勉強したり、仕事をしたりするからゆとりもまた生きてくるのだと思います。自らゆとりを作り出すことも大切だと思います。子どものうちはゆとりを作るのに親のサポートもいると思いますが、とにかく「ゆとり教育」は本末転倒だと思います。
学習塾で教えている立場から言わせてもらえば……(月夜桜・未婚・20代後半)
小・中学生を学習塾で教えています。関西にある少人数制の塾で、私立も公立の子も来ています。教えているのは、有名私立学校で上位の子から、公立で高校進学が危うい子までホントさまざまです。最近特に思うのは、年々、公立の子どもたちの、勉強できない子とできる子の差が激しくなっていることです。そして中学校の私立と公立の学ぶ内容の充実差がかなりあるのが気になります。傾向として言えば、私立はできる子に合わせて、公立はできない子に合わせてカリキュラムを組んでいるみたいなのですが、勉強内容が簡単になりゆとりができたって、やらない子はやらないんですよ。平均のハードルが低くなれば、成績の良くない子の取る点はそれに正比例して低くなるんです。できない子に合わせてゆとりの教育をって言ってるけど、公立の小学校は宿題を出さない先生とか、授業をあまりしないでテストとプリントばかりやらせてる(つまり教えるのをさぼっている)、保護者に言わせると『ハズレ』の先生がいるみたいなので、「公務員の教師のためのゆとり」だと思ってるんです。薄くてカラフルでキレイな教科書より、勉強がわかり成績の上がる授業をしてくれる先生のほうが、子どものために必要なような気がします。

子どもに多様な生き方の選択肢を与えるものでなければなりません(べんじゃみん)
私立一貫中・高の教員です。勤務先はもう数年間週5日制です。で、生徒は部活に行ったり、塾や習い事に行ったり、家族で出かけています。ただ、これでも進学実績に大きな落ち込みがないのですが、結局はそれは「わたし学だから」。そう、文部科学省の指導要領を外れた高度な内容を教えているので、「短時間でも高能率」ということなのです。今の公立の方法では、ただやることの量を減らしただけで、これでは大学受験に対応できないのは当然です。公立高校から有名大学を狙うためには、高校での勉強が本当に詰め込みになります。教科書が、昨年までと比べて本当に薄くなったと同僚同士で話し合っています。そして気になるのは、今の子どもへの進路指導は「勉強ができる」ことにばかり重きを置いていること。でも、現代はこれだけ価値観や生き方が多様化しているのですから、どんな職業でも一人前に食べていけるようになれば良いはずで、そして、大人はその選択肢を与えれば良いのではないかと思っています。
学校だけが、教育/勉強の場ではないと思います(アズミぷー・福岡・44歳)
中2の娘をもつ母です。わが家は、土曜日が休みになって親子ともどもゆとりがあってとても楽になりました。朝もゆっくりできるし、娘の習い事も土曜日にまとめて、一週間が有効に使えるようになりました。学力のことを考えると少し不安にはなりますが、勉強をしない子どもは、7日学校に行っても、5日行っても勉強しないし、向学心のある子は、いつでもどこでも勉強をしていますよ。わが娘は、7日行っても5日行っても変わらないタイプかな。たしかに、学校の先生に聞いてみると、先生たちも不安で、5日にしてほしいと思っている人はわずかだと思います。わが娘はあまり体力のあるほうではなくて、土曜日が休みになったことで、疲れが残らなくなって、体調がすごくよくなってます。それに、教室登校できない子や学校がストレスになってる子は、すごく楽になっていると思います。元気で何の障害もなく、親の手も他人の手も煩わすことのない普通のお子さんの親にとっては、物足りないものがあると思いますが、5日制になっての悪いところばかり指摘するのではなく、良いところも見てほしいですね。あまりにも、学校に何もかもまかせすぎていませんか? 土曜日の使い方は、親と子とで考えて過ごすのもいいのでは、と思います。塾でも良いし、図書館に行くも良し、野山や海に出かけたり、買い物に出かけたり、親子でいろいろできることもあると思います。土曜日に仕事のある親も多いと思います。わたしは、土曜も日曜も仕事です。父親の休みは不定期です。だからと言って反対するのではなく、親が仕事をしなければいけない現状を理解させるのもひとつの教育ではないでしょうか。それを理解し、行動することが、子どもにとってひとつの学習だと思います。ただ単に、子どもが家にいて食事の用意が大変だ、仕事があって一緒に過ごせないから、では、なんの解決にもならないと思います。土曜日の留守家庭教室をやってない市町村がたくさんあります。まずそこの整備から取り組むべきだと思います。5日制は、始める順番が間違ったために反対が多いと思います。土曜の留守家庭教室の整備と親の完全週休二日制の法制化、それから子どもの5日制とすればこんなに混乱もなかったし反対も少なかったと思います。縦割り行政の犠牲が子どもに回ってきたように思います。
問題は学習指導要領にある(かめちゃ)
マスコミでは「週5日、土曜日のお休みをどう過ごすのか!?」なんてことが話題になっているけど、もともと土曜日は隔週でお休みだったんですよ。残りの2回(or3回)がお休みになったから生活が激変! なんてあるんでしょうか? 少なくともわが家ではありません。もちろん、お仕事などの関係で「困る」という方もいらっしゃるとは思いますが、問題はやっぱり「新学習指導要領」にあるでしょう。「ゆとり」とか「総合的学習」など今ひとつ定義のあいまいなものが子どもたちの教育にどのような影響を与えていくのか……結果がみえるのは、それこそ10年先のことでしょう。「ゆとり教育」が「受験戦争」(古い?)の緩和につながるとは思えないし、楽しくなくてもがんばって知識を身につける努力は必要なのではないでしょうか? 物心つく前から親の意思でオリンピック目指してスポーツの英才教育をすることは美談になるのに、小さいうちから塾通いをさせると非難されるという風潮にも問題があると思います。
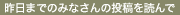
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
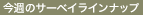
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録