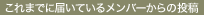

個人ではなく、組織としては(奥沢すずめ)
ボランティアの一人一人が、満足できることが、自己としては大切だと思います。ただ、ボランティアを束ねる組織としては、そのそれぞれの自己の満足が、いかに受け手の満足につながるか、ということを、組織的に配慮しなければなりません。もし、する側が仕事ではなく、ボランティアであるにもかかわらず、それに喜びを見出せなかったり、不満であったりしたら、受け手としても、心苦しいはずです。

まずはニーズを把握してから(omame)
ボランティアを希望するときには、自分が提供できることと、相手の意向をまず、聞くべきだと思います。福祉関係施設側から見れば、単なる善意の人よりも、仕事として、責任を持って取り組んでくれる人の方を、より必要としています。予算があれば、ボランティアよりも、雇用関係をきちんと結びたい。ボランティアをしたいと思ったら、まずどんなことで必要とされているのか、ニーズをきちんと把握し、引き受けた以上は、仕事と同じく、最後まで、責任感を持って取り組むことが大切だと思います。
I’m here for you(Kikumi)
テロ事件の雰囲気に、まだ飲まれている最中です。ボランティアも、人との関係であることには変わりなく、わたしは最初に「未熟なところがあったらはっきり教えてくださいね」と断ったあと、押し付けないようにしたいため、分からないときは、Do you want me to〜(わたしに〜をしてもらいたい?)と聞くことにしています。もちろん、何でもかんでもいちいち聞くわけではないですよ(笑)。話してもらうことで、相手のことが理解できるので、推測するより、ずっと回り道が少なくなります。I’m here for you(あなたのためにここにいますよ)という気持ちで何かしてあげたいならば、本人の望みをわかることが早道だと思います。
地域社会の中でステキな仲間たちができた(フレーバーママ)
依頼されて、中学生にスポーツを教えています。教えた子どもたちの中には、すでに社会人になった人もいて、今は、教える側に加わっている人もいます。小さなものですが、地域社会の中に、スポーツを通して、年配の方から、若い人たちまで集まった、ちょっとした楽しい仲間関係ができています。地域社会が、こうした関係の集まったものになれば、とてもすばらしいと思うのですが。ボランティアをしたおかげで、この一員になれたことをとても感謝しています。
好意が悪意に変わるとき(yomi)
家庭環境が不遇と思われやすいわたしは、多くの人が同情、好意を寄せてくれました。「あなたのために」という好意を拒否した時、その好意は悪意に変わります。ボランティアの中に、悪意に変わる何かがあるなら、それはもう、ボランティアとは言えないのではないでしょうか?
無意識のうちのボランティア(mmasae)
「ボランティア」って思って行動するよりも、自然と、自分の行動が、ボランティアだったんだ! と感じられるように、行動できたらよいな、と思います。優しさを少しだけ自然に出せたら……わたしの理想です。

ボランティアの押し売りはしてはいけない(steammilk)
たとえば、やっている本人は、「ボランティア」のつもりでも、相手にしてみたら「いい迷惑」なことってありますよね?相手の気持ちを考えず「自分のボランティア精神を貫くだけ」のボランティアは、かえって迷惑なこともある、ということなのではないでしょうか。わたしは中学生の頃、弦楽合奏部に入っていて、部の活動で、老人ホームに慰問に行きました。ほとんどの方は、涙を流しながら楽しんで、喜んでくださいました。だけど、中には「年寄りだと思って馬鹿にして! 」と叫ぶおばあちゃんもいました。ボランティアの押し売りはしてはいけないと、その時、学びました。
自分確認のためのボランティア(shizupon・東京・未婚・25歳)
わたしは、手話通訳のボランティア(?)をしています。ろう者のためとはいいながら、自己満足の部分もあると思います。これから結婚をして、出産、育児をしていく中で、自分確認のために、ボランティアがあっても、かまわないのではないかと思います。
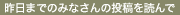
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
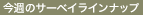
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録