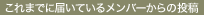

自分の育てられ方から学んだこと(あやたつ・千葉・未婚・24歳)
わたしは第一子の長女ということもあって両親から厳しく育てられました。昔のことで印象深いのはわたしが小学校5年生のとき、持久走大会で2位になったことがありました。長距離が苦手なわたしが2位になったことを父親は褒めてくれず、逆に「なぜ2位なんだ」と言って怒ったんです。1位が取れなかったことについて、どうしてそうなったかわたしに分析させたんです。答えられないと怒鳴られたりもしました。1カ月くらい、夕飯の時間はそのことばかりが話題になりました。そのたびに胃が痛くなったり、泣いたりしてごはんが食べられないことがありました。今でも家族とごはんを食べるのはなんとなく気が重いのは、そういうトラウマがあったからだと思います。親としてはそれが教育だったのでしょうが、わたしにとってはその後どんな出来事も、父親の顔が浮かんで積極的になれませんでした。しかし、そうやってつらい思いをして育ったからか、逆に友だちやパートナーがどんなに小さなことでも頑張ったであろうことは褒めるようにしています(この場合、褒めるといったらおこがましいですが)。自分に将来子どもができたとしても、自分が味わったような苦い経験はさせたくないと常に思っています。子どもを一人の人間として尊重し、褒めてあげようとする気持ちがあれば、子どもも自然に喜んでくれると信じています。
褒めて成長(あるばーと・神奈川・既婚・36歳)
子どものオムツがとれる前のある日のことでした。朝目覚めてからトイレに直行して「ちゃんとできた」のです。とにかく褒めて褒めて褒めまくりました。その日から、ピタリとオムツが必要なくなりました。乳児から幼児になった感動は親子共通のものであり、共感できたのだと思います。だから子どももわたしたちの気持を受け止めてくれたのだと思います……と書こうと思った昨日、3年ぶりにオネショをしてくれました(笑)。
一緒に喜ぶ(しょうっち)
ほんとに心からがんばったな、というときは、大げさにびっくりして褒めます。そうすると、うれしいいい顔がこちらを向きます。どうやって褒めようかということより、一緒になって喜ぶという感じを持つようにしてます。
目を見て抱きしめて、体でも表す(雑賀)
目を見て、抱きしめて褒めてあげる。言葉だけでなく体でも表現しました。子どももわたしも嬉しさが倍増したような気がします。
日常のちょっとしたことを褒める(binko)
わたしの場合は、生活のいろんなことを教えるとき。たとえば、玄関では靴を揃えて入ることを教えるとき、わたしが靴を揃えているのを子どもがじっと見てまねをしようとするのは誉めようと思いました。でも、わたしがそばにいなくても、玄関で靴を揃えることができているならさらに誉めて、「このようにしてくれるとおかあさんはとってもうれしい」と一言加えます。そうすると子どもも喜びます。このようなちょっとしたことを何度も繰り返せば、物心ついたときには、自然にそういうことが身についていました。でも、親の心が荒れていて、子どもを褒めることを忘れたりしたら、子どももまた荒れてしまいました。言うことを聞かないので、お尻をペンペンとしたら、ちゃんと言うことを聞いてくれたので、そのことを褒めたらすごく喜んでくれたことを覚えています。このとき褒めなかったら、素直さが欠けていったかもしれません。

褒め言葉に潜む「やる気への期待」を感じている?(ちゃぷちゃぷ)
褒め方、しかり方で葛藤中です。保育園入学当初、先生に「この子はやる気がない」と言われ、「褒めるとやる気がでる」という言葉に従い、いろんな場面で褒めてきました。でももしかしたら無理に褒めてる?と自分を振り返ることも……。同じ言葉で褒めてるのに、おばあちゃんが褒めるほうが張り切ったりするのは、わたしの褒め言葉に潜む「やる気への期待」を感じているのではないかと思うことがあります。一方で、初めて見たでんぐり返しを見て、心底すごい! と思って褒めたとき、子どもは何回も何回も得意になってコロコロ転がっていました。
過度にならず過小でもだめ(トリニティー)
おいっ子の面倒をたまに見ますが、褒め方って難しいなあ、といつも思います。過度になってもいけないし、過小でもだめ。あとタイミングも難しいなっていつも思います。
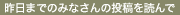
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
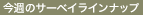
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録