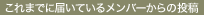

日課になっています(moomingmama・神奈川・既婚)
4歳の子どもがいますが、読み聞かせを0歳からしています。子どもにとっても、親にとっても良いことだと感じています。共働きの家庭なので時間との戦いですが、本棚から「今日のご本」を真剣に選んでいる横顔を見て、既読絵本の場合「一緒に声を出して読む」様子は、わたしの至福の時です。出版社から定期購読し、アマゾンでペーパーバックを買い、書店で子どもと選んだり、そして図書館で借りています。それにしても日本の絵本は高いですね。
図書館をフルに活用(rainyblue・神奈川・既婚・40代)
自宅の最寄駅の近くに公立の図書館があり、子どもが1歳の頃から家族全員が図書カードを持って毎週借りられるだけ絵本を借りました。下の子が生まれてすぐ図書館で聞いてみたら0歳でもカードは作れるということなので家族4人×一人3冊、つまり12冊を毎週借りました。気にいって再貸し出しを続けた本は買いました。エリック・カールの『パパ、お月さまとって』『だんまりこおろぎ』(ともに偕成社)、こぐま社のこぐまちゃんシリーズ、『どろんこハリー』『おやすみなさいフランシス』(ともに福音館書店)は、中高生になった子どもたちが今でも時々読んでいます。子どもが小さかったころ図書館のない生活は考えられませんでした。
本読みの時間(きりきり)
息子が1歳を過ぎたころから、毎晩寝る前が本を読む時間になりました。一種の生活習慣です。初めは本当に「絵本」でしたが、だんだん大きくなるにつれて、字が多くなり1冊の本を何日かに分けて読むことが多くなりました。こんなところに息子の成長を感じています。本を読む効用はいろいろ言われていますが、わが家ではお勉強的な「効用」よりも、母子の共通の時間を共有することのほうが大きいように思います。また、寝る前にワンクッション置くことで、落ち着いて眠りに入れるような気がします。今、1年生ですが、いつまでこの時間があるのでしょうか。大切にしたいと思います。語感の良い本は大好きですね。
その日はドキドキです(chokko・広島・既婚・30歳)
娘が通っている幼稚園では、「父の日参観」の最後のイベントとして、クラスのお父さん全員でじゃんけんをして勝ったお父さんが絵本や紙芝居を読みます。緊張しつつもなかなか上手に読むお父さんに子どもたちもくぎ付けです。「家で読むのと大勢の前で読むのとは違うのかなぁ」と、もし勝ってしまったらと夫が言っていました。

本が嫌いな子はほとんどいない(たみたみ)
わたし自身は子どもはいないのですが、学校図書館で働いていて、よく本を紹介しています。そこで感じることは「今の子は本離れなのではなく、本に出会う機会がない」ということ。「本なんて読まない」という子どもでも、「じゃあ絵本でも見てみたら?」と言うと絵本から入り、徐々に読みでのある本に至ります。そして、幼いころに大人に本を読んでもらった記憶のある子のほうが、「本で楽しんだ」覚えがあるので、本に入りやすいようです。ちなみに友人や同僚の子どもに人気の高い絵本は『そらまめくんのベッド』『そらまめくんとめだかのこ』(ともに福音館書店)『よるくま』(偕成社)『よるくまクリスマスのまえのばん』(白泉社)です。
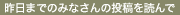
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
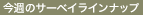
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録