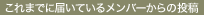

まずは自分から動く(just a moment)
このサーベイを読んで、かなり刺激を受けました。今まで自分の仕事が滞ったり、意見が通らないことがあると、上司が動かないとか、トップの判断を心の中で責めたりしていましたが、そんな姿勢が部署全体の風通しを悪くしていたような気がします。マインドやモチベーションて人にうつっていきますしね。今日から自分の頭から風を通していきたいと思います。
パーティションを配置換え(古川みゆき)
コミュニケーションは風通しの良さの基本。デスクの配置は、かなり影響します。わたしの会社は外資系で、マネジャーは普通パーティションによって部下と切り離されています。部長席と呼ばれるパーティションで囲まれたちょっと広めのスペースは部長のステータスのしるし。でも、かなりコミュニケーションの妨げになっています。思い切って、部下に混じって座れるように配置換えしました。結果、わたしが何をしているかも部下に直に伝わり、部下も質問しやすいと好評です。
自分ができることをする(Kit・大阪・53歳)
風通しの良い職場であるかを探るには、どのくらい情報が流通しているかではないでしょうか。工夫というほどのものではありませんが、立場が上がるにつれ、情報が少なくなりやすいことも事実だと思います。そこで、目線を下げ、担当者と同じ目線で物事を見るように努力しています。これって結構難しいんです。上司が部下のためにできることはないかを考えると、私的な相談に乗ることと、承認昇格のお手伝いくらいしか、現実にはありませんね。他はほとんど命令形の押し付けとなってしまいます。そこでは何かしても「してあげる」になってしまうんですね。これが部下にはたまらなく苦しく思える原点ではないでしょうか。自分ができることを上司も進んでしていくと、部下の見る目も少しずつ変わってきて、明るく話しやすい雰囲気が出てくると思います。
休んだ時のサポートがしっかり(aim↑)
前の職場では有給休暇・フレックス制度と充実はしてたものの、有給休暇どころか「今日フレックスで」とも普通に言えない雰囲気には得心いきませんでした。結局退職間際でも同じで、残したまま退職しました。現在の職場は休んだ時のサポートがしっかりしているので安心して働けています。制度だけでなく、こういうコミュニケーシュンの地盤があると、「特に用もないけど休みたい」がなくなるものだなと感じています。
「提案のしやすさ」が風通しの良さにつながる(mamick・パートナー有・37歳)
わたしがイメージしたのは「提案のしやすさ」です。IT系の部署に身を置いているわたしですが、小さいことでは、次期の取組みテーマについて、自身の守備範囲を越えた提言ができる。大きいことでは、社の商品企画について自由にユーザーとしての意見が言える、という風土があります。もちろんそれらは、同時に次回の自分の仕事のチャンスでもあります。
目上の方々とも仕事のアドバイスはもちろんなのですが、将来のビジョンやそのためのライフプランについてもざっくばらんに話をすることができます。マインドとして感じますのは「一度きりの人生を楽しまないと損!。いやいやする仕事は人生の無駄な時間」といったところでしょうか。今の苦労は絶対に次回へのステップになりますし、もしならないのであれば、即刻別の適性のあった仕事にシフトすべきだという考え方があり、同時に複数のプロジェクトが立ち上がる今の時期はメンバーは都度編成し、一期一会を楽しんでいます。
「ほうれんそう」の徹底(ブルー・30歳)
月並みですが、「ほうれんそう」の徹底だと思います。最近、職場の人間が増えてきて、誰が何をしているのか見えづらくなってきましたし、みながそれぞれ忙しいので、頼んだ仕事がどの程度進んでいるのか、報告がおろそかになりがちで、頼んだわたしも自分の仕事に追われて催促をしないまま、というのが結構ありますが、最近、これではいけない、自ら「ほうれんそう」をきちんと実行しようと強く思っています。
基本的に組織はフラット(はるたいママ)
非常に単純なことで、うちは外資系だからかもしれませんが、肩書きで呼ぶことがありません。全員「さん」付けか、下の名前やあだ名にさんを付けます。なので、よその会社の人に「御社の●●社長」と言われて、「あ、そういえば、彼が社長なんだよな」とか「部長だったんだな」と思うくらいです。基本的に組織はフラットで、全員が前線で戦う集団を目指しています。マネジメントだけやればいい、と思う人が出た時点で組織が陳腐化するような気がします。
常識をわきまえたフランクさが必要(あるばーと・神奈川・既婚・36歳)
3日目のブルーさんの発言に同感です。さらに、ビジネスとしての共通言語で会話できるかとか、ささいなマナー的なことまで規制しなければならない状況を必要としない職場環境を保てるかだと思います。「社員は家族だ」とおっしゃっている組織もありますが、親しき仲にも礼儀ありのとおり、常識をわきまえたフランクさが必要だと思っています。

社内草の根ネットワークを活用(yukachan)
比較的若い人たちは情報を共有したり、議論しようとするのですが、年配(肩書きにこだわる上の方)は拒絶反応の状態です。報告一つも自分より上の人すべてに説明して歩かなければならず(メールを自分で読まない人が多い)、途中でもみ消されることも少なくありません。下手をすれば最悪の評価の上、リストラ対象になるという、とても古い体質ですが、それを打破しようと社内草の根ネットワークを活用しながら日々戦っています。お給料もボーナスも切り詰められる中、せめて風通しは良くなってほしいものです。
中間管理職の段階で滞る(0310Rikako・神奈川・30代)
コーポレートカルチャーレベルの話なので、仮にその会社全体の風通しが悪い場合には、トップのコミット、全社で共有、中間管理職のどこかで滞っていないかしっかりチェック、することが必要です。最終的には、それを実現するために、組織や管理職をどう動かすかのトップの力量のような気がします。どのくらい難しい話かという点で例を挙げると、外資系でフラットな組織なわが社でさえ、一生懸命トップがコミットしても、中間管理職の段階で滞ることがよくあるからです。
「面倒な相談をしてくれるな」という雰囲気(ururu・東京・パートナー有り・30歳)
今の職場は人数も減り、会社全体の業績悪化もあって殺伐としているので、ちょっとしたことで人を追い込む(=辞めさせる)という空気が漂っています。コミュニケーション不足や、反対に言葉を並べすぎることで誤解が生まれるのが一番怖いので、「忙しいモード」の人にはメールで、そしてなるべく軟らかい簡潔な表現で詳しく述べるようにしています。でも今はみんな「面倒な相談をしてくれるな」という雰囲気なので、本当に困っていることは、なかなか相談できなくなりました。
属人的なところが大きい(xyz)
結論から言うと、風通しのいい職場は「そうそうない」のでは、と思います。風通しを良くするのは職場ではなく、人間関係の問題だからです。人間関係の問題となると、極めて属人的な問題になります。となると、一筋縄では行かず、万民に通じるような法則はなくなるのです。上司は選べません。いくらファシリティーが整っていても、上司によってはマイナスに作用する場合が多々あります。人に合わせて何かをするという状態は、工夫ではないように思います。
自分は転職を重ね、今いわゆる外資系のコンサルティングファームにいますが、ファーム内でも独特の雰囲気があります。珍しいことに、ファーム内で部署異動をしたのですが、前のチームのパートナーは、極めて陰湿な日本人的な側面を持つアメリカ人で、封建的でした。
一方、異動後のチームは日本人ばかりですが、極めて外資系的で、言いたいことはたとえ相手がパートナーでも直接ものを言える雰囲気があります。どちらが仕事をしやすいかと言えば、当然後者であり、仕事でいくら遅くなっても、ベストなものを作り出そうという雰囲気が自然と芽生えます。前のチームでは、パートナーを信用している人などほとんどおらず、政治的に長けている人のみが勝手にやってることがとても多かったです。やはり属人的なところが大きく、工夫を重ねてもダメなものはダメになってしまう傾向がありますね。
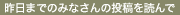
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録
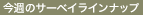
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録