ホーム
> news &policies > 規制改革メルマガ
> vol.12
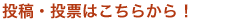
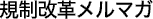
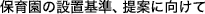
2001年10月5日(金)
今回のご意見テーマ
「(設置基準が作られた場合、)基準に満たない既存の認可外保育所はすぐに閉鎖にすべき?」
提案する、ということは具体的に、現実的にも考えをおよぼすことです。安全な保育園を、という基準作りを求める一方で、それ以下のところを短期間で閉鎖することには反対という人が圧倒的でした。
しかし対象者は、選択している親ではなく、物言えぬ子ども。どれだけ短期間で改善できるのか、どれだけ短期間で別の保育所を見つけられるのか、短期間、とはどの程度かなど、以下のご意見をお読みいただいてから、続けてご投稿ください。
ewoman:規制改革メルマガ編集長
佐々木かをり
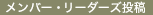

アドバイザーを派遣する(mashi)
確かに保育園の基準はあったほうがいいと思いますが、だからといって基準に満たしてない園を閉園するのは、預けている親やそこに働いている人のことを考えると適切な処理ではないと思います。園の経営者も苦しい中、突然規制ができましたと言われては大変ですよね。保育園の基準を設定した場合、基準ができましたよと自治体で通知するだけでなく、その基準に近付くためのアドバイザーを派遣したりするのはどうでしょうか? 現実問題、そのお金はどこからという話になるのでしょうけど。保育園問題は実際通っていると深刻ですが、子どもが成長して卒業すると、次の問題が発生して継続で改革を求めるというのは難しいかもしれませんね。次の世代に上手く伝えていく方法も必要ですね。
改善の手助けを(rizucherry)
一律的な基準による判断だと、その園の内容や実情も考慮していないこともあるから、まず、広さ・保育士・衛生面・安全管理などで振り分ける。そこで満たしていないものが、改善できるように、手助け、あるいは統合などの形で運営できるようにしていくことがよいと思います。必要に迫られて、基準を満たしていなくても存在できている現状を見れば、閉鎖ではなく、存続できる環境にもっていくことが望ましいですね。ただ、事件を起こしている園のように、内容的におかしいと思うところについては、論外と思います。
情報公開をうまく活用できないか。(イエペ)
設置基準がどういうレベルになるにせよ、一律に基準に満たないから即閉鎖というのは、個々の園や、その地域の事情もあり問題があるのでは。また、前にも書きましたが、認可外のよさと言いますか、「行政に頼らずにがんばる!」という自主独立の気風のある園だってあると思うのです。ですから、まずは佐々木さんもおっしゃっていたように、情報公開を行うことでしょうか。このような設置基準ができて、あなたの園はここが基準を満たしていないので、期限までに改善されないと、保護者をはじめ一般に公にします、ということでしょうか? しかし、改善の費用はどうするのでしょう・・・、難しい問題です。また設置基準を満たしていると、「認可外」という言葉は不適切になってくるような?
受け皿の用意を
認可外の保育園を利用している人のことを考えたら、一律に閉鎖するのはあまりにも乱暴すぎるのではないかと思います。たしかに、認可外保育園の基準にも満たないということは、保育の状況がかなり悪いということになるのでしょうが、受け入れ先がなければどうしようもないのです。まず、個々の保育園の状況を確認して、たとえば少しの援助で認可外保育園の基準を満たせるようにできるのであれば、ある程度の猶予期間をつけて自治体などが援助するとか、新規の認可保育園を増やして受け入れ先を確保するとか、まずそういった受け皿を用意しておく必要があると思います。それと同時進行で、あまりにも状況の悪い保育園については、改善命令を出して、それでも改善されないのであれば、そのときは閉鎖するしかないと思いますが、そのときにも利用者が不利にならないように、何かしらの受け皿を自治体側で用意してほしいです。
子どものために1日も早く改善を(べんじゃみん)
まず、すぐ閉鎖することには「NO」です。危険な施設とはわかっていても、ほかの預け先がないから、やむを得ず、という人が多いはずです。でも、そのまま放置しては「ちびっこ園」再発にもなりかねません。そこで、警告を発したら、必ず官報やHPで発表し、また、親にも通知して、園にも当然改善を命じます。6カ月などの期限を設け、それで改善されていれば良し、されていなければ閉鎖、ということでよいのではないでしょうか。
多面的にランク付けして公開を!(のんびりママ)
たしかに基準に満たないとはいうものの、実際に十分な受け皿がない中で廃止されては、困ったときの預け場所がどこにもなくなってしまいます。そこで、認可/無認可の2種類で評価をするのではなく、認可および無認可園を人材、施設面から複数段階にランク分けし、その情報を公開してはどうでしょうか。緊急度、経済状況等々、父兄の状況に応じて選択の幅を広げ、かつ父兄がそれを認識できることが重要だと思います。これにより、保育園経営側もそれぞれの特徴を出しやすくなるのではないかと思います。
保護者への連絡を(ビッキー)
基準を満たすように即改善できるところはすればよいのではないでしょうか? すぐにできない場合はその旨を園児の保護者に伝え、それを了承の上で、保育を実施すればよいのでは。基準に満たないことが判明した時点で、すぐ閉鎖してしまえば、そこに通っていた子どもたちはどこへ行くのでしょうか。ただでさえ保育園が不足している世の中なのに、そう簡単に基準だけで決めつけてしまうのはどうかと思います。たしかに基準は絶対必要だとは思いますが、基準を満たしていないということをちゃんと公開し、改善中だと保護者に伝え、それで納得いかなければほかの園に移るのでもいいし、納得していただけるのならば、それはそれでいいのではないでしょうか。
情報公開と保護者啓蒙(mamarin)
たしかに非常に難しく、お役所仕事の煩雑さが最も発揮されてしまいそうな分野です。この対処には情報公開と保護者啓蒙しかないと思います。こうしてメルマガに参加していても、法的な事などよく理解できないくらいですから、一般の保護者に対してわかりやすいようにその施設のグレードを示す方法があればいいとは思いますが、それが浸透、法制化、拘束力を発揮するまでには気が遠くなるような時間がかかると思います。その間犠牲になる幼児が出ることは黙認できるはずがありません。ですから次の二つを提案します。
- 情報公開について 営業許可を出す機関が監督責任としてその施設の現状を表示する事を義務付ける。それは各施設の入り口に(よく工事現場にあるような)プレートにして、責任者名、有資格者数、調理責任者名、園児数(在園/定員)、1人当り平米(ベッド数)、などを掲示する。消防署、保健所などの検査認証印もそのプレートに併記する。苦情などを取り扱う相談所を設置しその連絡先も明記する。また、保護者が求めた場合には、これらの情報を提示することを義務付ける。保護者からの苦情が多い施設には監察官を送り込み指導を実施する。改善が見られない施設には警告、さらに閉園にするなどの措置を取る権限を監督機関が持つように(早急に)法整備することが必要。
- 保護者への啓蒙 婦人科、小児科など医療機関、玩具店、子ども洋品店、ファミレス、コンビニなどの店舗、妊産婦向けの雑誌、さらに高校や短大などの家庭科、福祉科などの授業にてこの問題を喚起するようなパンフレットや記事を使用し、現在の、そして未来の保護者にも保育の問題を提起し啓蒙を行う。結局のところ、預ける親の意識や知識の欠如が施設の暴走を許し助長するのであるから。

保育所選びも親の自己責任のもとに行われるべき(south44)
そもそも保育所設置基準の設定自体に懐疑的ですが、今回のテーマはより非現実的だと思います。劣悪な保育所を許せないというお気持ちはわかります。それがイヤならそういうところには預けなければいいだけの話ではないでしょうか? なぜそういう保育所であっても預けざるをえない子どもがいるのか? 保育所の数が足りないからでしょう。そこで設置基準に合わない保育所を閉鎖させれば、ますます保育難民が増えるのでは? 基準を満たす保育所があったとしてもそれはそれでコストがかかるでしょうから、金銭的な理由で預けられない家庭もいっぱい出て来るでしょうし。たとえは悪いですが、病院で手術を受ける際には、失敗しても免責ということで患者側は一筆とられます。他者に子どもを預けている時点で、親はそのリスクをも覚悟すべきです。事故が起きるのは大抵乳児期までの子どもなのですから、事故が怖いのならそのあいだくらい自分で世話をしてみるのもひとつの選択ではないでしょうか? どっちにしろ保育所選びも親の自己責任のもとに行われるべきで、まずは保育所の情報開示を徹底させることが大事だと思います。「非認可保育所=悪」という短絡的な考え方には反対。
自治体ごとに保育事業を統括する機関の設置(文月)
昨年の朝日新聞で「21世紀職業財団」(労働省の外郭団体)の育児支援事業を紹介していました。事業の一つは、保育サポート事業。育児を終えた女性などを対象に「育児サポーター養成講座」の開講。サポーターはそれぞれの地域で登録されます。サービスの内容は、保育園の送迎、学童保育終了後の一時保育、親が病気になったときの保育などで、利用したい人は都道府県に設置された電話窓口に申し込んでサポーターの派遣を受けます。さらにこのサービスの拠点としての「ファミリー・サポートセンター」建設への補助事業。労働省が補助金を出し自治体が設置します。また、今年の記事では、「駅前に保育ステーション設置」の方針が取り上げられていました。保育所作りを中心とする「施設型」とは別に、こうした形のサービスもどんどん広がっていく必要があるということなんでしょう。でもサービスが多様になるということは、それだけ選ぶほうにも判断する力が要求されるということです。そうした判断が的確にできるような、地域の保育事業を一貫して管理、監督し、加えて住民への情報提供および利用者側からの問い合わせ、苦情処理にも対応するような機関があればいいのではないかと思います。
|

|
|


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について