ホーム
> news &policies > 規制改革メルマガ
> vol.11
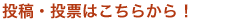
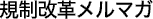
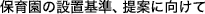
2001年9月28日(金)
今回のご意見テーマ
「認可外保育所にも設置基準は必要?」
非常にたくさんのご意見を頂戴しました。「設置基準はあるべき」が、圧倒的。以下がみなさんからのご提案です。来週のメルマガで次のステップに進むまで、まだお返事いただいていない方、どうぞご意見をお寄せください。
ewoman:規制改革メルマガ編集長
佐々木かをり
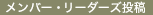

やはり認可保育園のほうが……(のんびりママ)
わたしは来年4月からわが子を0歳児クラスに入れるべく、現在、認可および無認可保育園を見学中です。その中で感じることは、保育環境はもちろんのこと、保育士の質もかなり違いがあるということです。食事のマナーに対するしつけ、悪いことをした場合の叱り方、ものの与え方などに関してそれぞれ観察したのですが、やはり認可保育園のほうが保育士の方の質が全般的に高かったことは否めません。保育士の数も安全面では必要な基準ですが、やはり、ただ子育て経験があるというレベルではなく、ある一定期間どこかで研修を受けさせるとか、定期的に能力を評価するシステムで保育士の質の安定を図らないと、いくら保育園の数が増えても預けられるものではないと思います。
保育の「質」を大切に(norico)
いま、小学校3年生の娘の産休明けから、引っ越すまでの3年間、無認可である「共同保育所」に預けました。共同保育所とは、行政ではなく住民たちが、場所と保育者を確保して、自主的に開設したものです。その保育内容はというと、0歳児クラスは、認可保育所並みに、赤ちゃん3人に対し保育者1人がいて、まだハイハイもできない頃は、保育者が1人ずつ抱っこして、お散歩に連れて行ってくれました。小さな保育所でしたが、常勤の調理師が給食やおやつを手作りしてくれました。母乳を凍らせて持っていくと、昼間に解凍して、わが子に飲ませてくれました(おかげで、1歳で断乳するまで、何とか母乳は出続けました)。夏は朝・夕、冬でも悪天候でない限りは必ず毎日1回、お散歩に連れ出してくれて(実はお散歩には危険がつきまとうため、保育者の方が緊張して大変なのです)、自然と触れ合い、体を動かして遊ぶことを大切にしてくれました。おかげで、娘はとても丈夫に育ちました。設置基準は必要だと思いますが、その基準は、上記の共同保育所の保育内容のように、「保育の質」を大切にしたものであってほしいのです。
認可保育所に準じた基準は必要(peacerose)
保育所の開設にあたっては、市町村が厳しくレベルをチェックし、警察、消防、保健所なども定期的な見回りを行ってほしい。認可保育所と同等であるべき基準としては、保育士の人数、衛生、安全基準。ただし、保育士および看護士の資格を持っていなくとも、子育て経験のある人で一定の研修を事前に受けた人などは、その人数に含めてよいと思う。一方、園庭については、都市の駅近郊の土地にそのスペースを求めるのは厳しいので、近くに公園や散歩のできるコース(川や木々のある)があればよいのでは。また、子ども1人当たりのスペースも、認可保育所より、やや手狭になっても仕方ないと思う。
「園庭」を絶対にするのはこまる (ゆず)
わが家がお世話になっている保育園は、認可外ですが、「横浜保育室」という自治体レベルの「認定」になっているところです。園の姿勢として、認可最低基準に疑問があり、認可園になることを目的とすると「いまやっている保育の質を下げることになるかもしれない」、ということもあって、認可基準クリアを最終目的にはしておりません。基準は必要ですが、それにより、画一された保育園ばかりができてしまい、園の存在自体が「孤立」してしまうのではないか、とも思います。たとえば、「園庭」がないばっかりに(寝具や室内環境は抜群でも)認可基準が達成できず、廃園になるのはこまるような気もします。
親への情報公開を(きさらぎハニー)
保育士の人数は基準33条2項の倍はほしいです。環境についていえば、子どもの成長過程で必要な、運動機能を妨げない程度の広さ(指導監督基準の1.65平米は少ない気がする)や五感を育てるのに必要な遊具の設置などは、最低限必要かと思います。施設は、当然ながら生命を脅かすものの排除の規定などが必要です。衛生面においては、週1回の施設の消毒規定もあればいいと思います。トイレの基準は、20人に1つは少ない。10人に1つは必要。あと、一番気になるのは、親への情報公開だと思います。家庭での虐待しかり、園での虐待しかり、明確なチェック体制と指導体制を構築してほしいです。
子育て経験者を入れることに賛成(tarsh)
子育て経験者を保育園に入れるという意見がありましたが、これに大きく賛成します。ただし、命を預かる職場で働く以上、プロ意識に徹してもらう必要があります。またキャリアへつなげるために、明確な立ち位置を決めることも必要でしょう。これは雇用の促進と流動化につながり、潜在的に眠っている力を外に引き出すことも可能にします。資格制度を確立し導入する事は可能でしょうか? 性を特化した資格になる可能性もあり、もしかしたら人権上の問題もあるのかもしれませんが、決して高く厚い壁ではないと信じます。
準資格みたいなものがあれば(どろまり)
子どもを預かる上で設備の基準は必要だと思います。衛生面、備品等の設置等々。保育士の数の基準も必要だと思うけど、資格と共に子どもが好きなこと、子どもを育てたことのある人を含めることも必要ではないのでしょうか。資格はないけど准看護婦のような経験での準資格みたいなものがあれば、子ども好きで保母さんになりたかったけど学校へ行かなかった(行けなかった)若い人たちなどでも、従事したいと考えてる人は多いはず。特色ある無認可保育所で、親から選ばれる保育所が増えればいいと思います。
企業のプレゼンにあきれました(Lisa)
いま、娘が来年から行こうとしている児童館/学童保育の公設民営化のプロジェクトが進んでます。先日、候補の企業のプレゼンがあったのですが、その内容を見ると「この人たち、子どものこと何も考えていないんじゃない」と思わずにはいられないものもありました。設置基準があっても,こんなにひどい内容を考えてくる企業があるというのに、これで基準がなかったらと思うと、それが許されている保育園があると考えただけで恐ろしいです。
保育内容の情報公開の義務付け(marinco)
基本的には、公立の保育所と同じくらいの厳密な設置基準があることが望ましいとは思いますが、施設面に関しては、あまり厳しすぎると無理があるかも。現実に、雑居ビルの中にありながら、志の高い保育者たちが、純粋に子どものための保育を行っている認可外保育所もあります。防火カーテンが購入できないくらい大変なやりくりの中で、良心的に精いっぱい子どもの保育をしてくれているところもあります。大切なのは、いかに設備が充実しているかではなく、その保育所の理念や保育の中身。外面的な設置基準だけでなく、どんな保育を行っている保育所であるかの情報公開を義務付けることではないでしょうか? たとえば、見学はいつでも求められれば許可しなければならない、とか、体験保育の義務付けとか、役所でも、すべての認可外保育所の保育内容を(施設の広さや保育者の数などだけでなく)把握できるようなシステムにして、利用者がページをめくりながら比べられるようにするとか・・・。認可保育所だろうと、認可外だろうと1番大切なのは、保育の中身です。それがオープンにされるような基準作りを希望します。
保育士の数は増やすべき(mamarin)
認可外保育所でも、保育士の数の基準は必要だと思います。「文月」さんの意見に賛成です。現基準の2倍は必要だと思います。3歳児に20人に1人は少なすぎます。「有資格者1名は必須で補佐(アルバイト、育児経験者など)1名でもよい」とすればいいのではないでしょうか。給食設備に関しては実際問題難しいと思いますので、業者などに基準を当てはめケータリングをする手もあります。ただしミルクなどを清潔に作るスペースは必要ですね。園庭はあればいいに決まっていますが、認可外の場合、場所の利便性などが売りになることもあるので、狭く劣悪な園庭を道路のすぐ脇に造るよりは、園内の施設を充実させ、あとは園外保育として、最寄りの公園に行くなどしてもよいのではないでしょうか。
「保護者との連絡」も重要(文月)
「設備に関して」ですが、「園庭は必須」、それから「園児の人数に応じたトイレの数を具体的に定める」必要も感じます。そして、保育室を2階、3階以上に設ける場合は、現在の指導監督基準に述べられている建築上の基準を満たしていることは当然として、特に緊急時の対応についてのマニュアルが明確に定められていなければならないと思います。最後に重要だと思うのは、「保護者との連絡」。指導監督基準にあるように、「連絡帳又はこれに代わる方法」により園と家庭の様子を連絡し合うこと。「緊急時の連絡体制が整っていること」。これも、明確にしておきたい点です。

設置基準よりも情報公開を(chiaki)
基準というものは、とかく抜け穴があり、既得権的なものになりかねません。それよりも保護者が自分に必要な情報をもとに、自分の責任で園を選ぶべきと思います。そのために必要な情報をできるだけ公開してほしい。特に預けている父母の生の声を聞けるシステムとか、行政区域ごとに掲示板を持ち、そこに保護者の書き込みができるようにし、それを誰でも見られるようにできれば、かなり情報交換ができるようになるのでは? 忙しくてコミュニケーションが取れない保護者同士の情報交換にもなるはず。問題点はデジタルデバイドでしょうか……。
|

|
|


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について