ホーム
> news &policies > 規制改革メルマガ
> vol.10
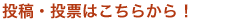
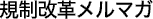
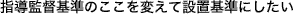
2001年9月21日(金)
今回のご意見テーマ
「認可外保育所の指導監督基準は甘すぎる?」
すばらしいご意見の数々、ありがとうございました。 変な言い方ですが、ewomanメンバーのパワーが集約されてきているようです。 掲載はできませんでしたが、投稿常連の「園長」さんのメッセージにもお褒めの言葉があり、嬉しい限りです。
とにかく具体的なご指摘ばかり。 次回のメルマガでは、ここを整理して第2ステージに移りたいと思います。 ですから、是非みなさん、読んでいただき、引き続きご意見をお寄せいただけると幸いです。
石原大臣に手渡した、今までのすべての投稿は、大臣から内閣府の規制改革スタッフにもめぐり、「読むように」と言われているようです。
子どもたちのためになる改革ができるように、と思います。
ewoman:規制改革メルマガ編集長
佐々木かをり
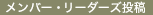

認可外保育園にも骨抜きでない設置基準を(yukina)
現在の指導監督基準は「望ましい」とか曖昧な表現が多い。認可外保育園でも、大切な子どもの命を預かるのは認可保育園と同じ。「守らねばならない」基準を明確に作り、定期的に立入調査し、守っていなければ罰則も必要である。基準としてわたしが特に重視したいのは、部屋の広さに対して預かる子どもの人数が多すぎないこと、子どもの人数に対する保育士の数は認可保育園と同程度にすること(認可保育園の基準でも子どもの数に対する保育士の数は決して多くはないと思う)、トイレや給食室の衛生・安全面について、たとえば消毒は週に何回といった具体的な基準を設けることなどである。
保育士の人数の基準は必要!(シーラカンス)
子どもの数に対する必要な保育士の人数の確保は、絶対に必要だと思います。「命」を預かっている以上、保育士の目の届かなくなってしまうぐらい大勢の子どもがいると、どうしても「ちびっこ園」のようになってしまうと思います。必要なスペースなどの問題もありますが、まず第一に子どもの「命の安全」が優先される、保育士の数の確保が必要だと思います。
「事故防止」と「すこやかな成長」、2つの観点から必要(Jerry)
事故防止の観点から、安全基準は絶対に必要だと思う。給食設備やベッドなどの設備、避難設備がこの範疇に入るのでは。子どものすこやかな成長という観点では、ごくゆるやかなガイドラインがあればよいと思う。いまの状況で存在する良心的な保育園が存続できなくなるようなことがないように、ガイドラインの内容が決められるべき。
利用者が判断できる情報開示のフォーマットを作ったら(奥沢すずめ)
すべての保育所が同じ基準を満たすべきという規制ではなく、利用者が判断できる情報開示のフォーマットを作ったらと思うのです。たとえば、保育室の平米数、過去数カ月の給食のメニュー、保育士の時間ごとのローテーションの人数など、具体的に細かく記載し(嘘がないように調査もして)、それを利用者にも見せなければならないような仕組みにすればと思います。利用者はそれを見て選択(環境が不満でも納得の上で利用するということも含めて)できます。また、不満があれば家庭内で気を付けるようにするとか(たとえば栄養的に心配だったら、家でフォローしたり)、要望したりもできるでしょう。園サイドでもどこが不備かわかりますし、経営を考えて、自主的な改善を促すきっかけにもなるでしょう。
複数の基準があってよいのでは?(しろうさぎ)
いままでの保育所や幼稚園とかの狭い枠内で、消極的な基準を設けて数を増やすのではなく、多くの女性にとって、実際に必要な「子どもを安心して預けられる場所・人」を、まず最初にあれこれ考えてみてはいかがでしょう。簡単に、短時間からでも安く預けられる託児施設はありがたいです。値段は高くても、良質の保育内容や特殊指導をする保育所も大切です。広々とした環境で、遊び中心の保育所も、元気な子には必要です。それでは、次にそれぞれの場所には、どのような基準が必要でしょうか。設置基準は、決して一様ではありません。保育所の在り方に沿った、それぞれの基準があってしかるべきでしょう。さらに設置基準だけでなく、それらの保育施設がその後安定して、保育事業に専念できるにはどうしたらよいか。そこで働く人たちに、気持ちよく安心して仕事を続けてもらうにはどのような方法があり、国としては何ができるか。その辺りのことまで真剣に取り組んでいただきたく思います。
保育者はすべて有資格者に(文月)
現在の指導監督基準に変更を望む点を、具体的に書き出してみました。 「保育に従事する者の数及び資格」に関して。
- 「保育に従事する者の概3分の1以上は保育士及び看護婦の資格を有するものであること」。これを、〈保育に従事する者は、すべて保育士の資格を有していること〉に。
- 配置される保育士の数について「2歳児 幼児6人につき1人」を、〈幼児3人につき1人〉に。同様に、3歳児は〈10人につき1人〉、4歳児以上は〈15人につき1人〉に。
あと、メルマガに園庭の話がありましたが、0歳児はともかく、幼児には園庭は必須だと思います。いくら近くに公園があっても、都心では幼児が自由に行き来できるわけではありませんから、かなり無理があるかと思います。〈ある程度の規模の園庭があること〉もやはり基準としてはじめから規定しておいてほしい項目だとわたしは思います。
規制力と弾力性をもったガイドラインが必要!(designhoops)
- 保育士と補助をする人員は規定して常時チェックすべき。 保育園を選ぶ際にあちこちの保育園を見学して、やはり認可と未認可では明らかに子どもたちの姿が異なりました。大久保に、珍しく民間の認可保育園があります。経営面、保護者の安心感、利用者のニーズ、子どもたちの保育環境等を考慮して何とか認可を取得したそうです。一方、近所に昔からある民間の認可外保育園では、保育士の方が疲弊した表情で利用案内をしてくれましたが、うずたかく積まれた紙おむつでふくらんだゴミ袋のすぐ横に、幼児のおもちゃ(幼児はおもちゃを舐めます)が転がっていて、食べ物のにおいも、使用済みのおもちゃのにおいも混濁していました。それでもほかに預けるところのない親たちが子どもを預けにくるのです。標準のルール化はぜひ必要です。認可保育園でも保育士の手が十分とはいえません。規定の保育士を備えている園には公共がバックアップすべきです。
- 衛生面の基準は必要不可欠。 認可保育園であっても子どもの伝染病(水疱瘡、手足口病、突発性発疹等々)は一人出れば必ずほかの子どもたちにも流行ります。認可園レベルの基準は必要です。
- 施設面では防災安全面の基準が不可欠。 広さの基準はゆるやかでもよいのではないかと思います。ただし2階建てで、2階部分に0〜2歳児の保育室があるような場合、災害時に自分で歩けない子どもたちが上階にいて大丈夫なのかと不安を感じます。ですから、安全面での避難路確保、災害時の対応修練は必要だと感じます。

経験重視で(rizucherry)
保育園に通わせた子どもも大きくなり、いまの方の悩みはよくわかります。当時思ったのは、資格のある若い人がほとんどで、子どもを産んだことも、育てたこともない人ばかりでした。たしかに、いい方が多かったと思いますが、こちらが教えることも多かったです。なので、資格にこだわらず、数名は子育て経験者がいればと思ったものです。子どもにとって、安心して過ごす場所にするべきと思います。
近頃何かがおかしい…… (そら)
最近保母さんが子どもを死なす記事がよく出てますね。子どもを持つ親としては、どこに預けるにしても大丈夫なんだろうかと躊躇してしまいます。女も働く時代です。預ける人数が多すぎて保母さんが足りない状況かもしれませんが、信頼して預けるわけです。まあ自分の子でさえ大変なんだから他人の子なんかだと余計ですよね。信用してないわけではありませんが、認可の下りてない、資格のないっていうのがきっと多いと思います。もっときちんと管理してほしいものです。
|

|
|


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について