ホーム
> news &policies > 規制改革メルマガ
> vol.4
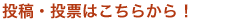
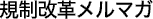
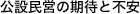
2001年8月10日(金)
今回のご意見テーマ
「保育所の公設民営化、不安はありますか?」
今回も具体的な体験・経験をもとにした説得力のある投稿を送っていただき、ありがとうございます。保育所の公設民営については、みなさん総論としては賛成のようですが、不安な点、懸案事項も少なくないようです。KUROさんやomy13さん、園長さんが指摘するように、保育士や職員の処遇、さらには、補助金の問題も非常に重要な問題です。この問題は、もう少し勉強した上でテーマにしたいと思っています。
ewoman:規制改革メルマガ編集長
佐々木かをり
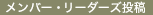

保育所は内容の充実を優先(しろうさぎ)
わたしは女性の社会進出をサポートする目的から、小さなベビーシッター会社を経営しております。保育所には仕事柄あちこち伺いますので、公立、私立、無認可・・・と状況の違いを肌で感じます。わたしは母親の側に立った視点でいまの仕事を続けていますが、保育所の経営・運営は、非常にデリケートな部分の多い仕事だと感じます。
数時間、お子様をお預かりするベビーシッター業務でも、効率と経営を最優先させた大手企業の内容・実態は、決して充実したものとは言えないのが現状です。まして毎日長時間、しかも0歳からの数年を過ごす保育所にあっては、何よりも内容の充実が優先されるのではないでしょうか。民営化を悪いとは思いませんが、景気や市場原理の影響をモロに受けながらの保育サービスは、最も大切な「人間を育てる」理念を見失いがちになると感じます。かといって、現在の認可のシステムでは、あまりに均一化しすぎていますし、入所者への審査基準も不可解です一人ひとりに援助が下りているのに対し、専業主婦が育てる場合は、保育に一銭の援助も出ず、すべて自腹を切っている点も変な話です。母親が仕事をしていて、保育できない状態だから公的援助を出す、といった発想は「両親で子どもを育てる」「両親で働く」現状からは完全にズレています。
保育士の処遇と保育の質(KURO)
民営化により、保育所の運営経費が約半分になると聞きます。もっとも節減されているのは、人件費でしょう。公立保育所の場合の、30代後半で800万円という金額が妥当かどうかは別にして、民営化の場合の保育士に対する処遇は、十分なものと言えるでしょうか。契約社員で月額15〜20万円という仕事を、一生続けようと思う人はどのくらいいるでしょう? 保育とは、人を人が育てる大切な仕事です。数年で辞めていくのを前提とした処遇で雇われている人に、そんな大事な仕事を任せるのは無茶だと思います。もちろん、公立保育所のように、年功序列で何も努力しなくても、年々報酬が上がるような仕組みにせよ、と言っているのではありません。また、処遇をよくしたからといって、必ずよい保育ができるようになるとも思いません。しかし、よい保育をするためには、その仕事を一生続ける、という選択肢が十分に成り立つような処遇は、必要条件ではないでしょうか。公設公営が民営になったとたん、経費が半分になるというのは、あまりにも極端だと思います。目先の経費節減だけではなく、「保育」という事業の持つ社会的な意味、長期スパンで見た影響まで考えない、安易な規制緩和には反対です。
公設民営保育所の不安材料(mamarin)
保育所の公設民営化に賛成です。理由は
- 公の限界が明らかであるから。たとえば、門には下手くそな動物の絵が掛かっている、各保育所はコの字型に配置され、下駄箱、タオル掛けなどが無造作に美的感覚なく置かれ、保母さんたちはみなジャージーで汚れてもOKという格好で、園庭は土で古臭い遊具がぱらぱらと配備されている。こうした「これが保育所(あるいは学校)」というイメージを決めつけているのは誰か。それは役所である。同じコストをかけてもっと気の利いたデザイン(というコンセプトは役人には皆無であろう)を取り入れたり、保育の内容にしても、新しい試みをできたりするのは民間の、それもその道のプロであろう。
- 完全に民営でないほうがいいから。ニーズが多様化しているので、供給側も多様化されることは歓迎です。しかし、メルマガにもありましたが、保育は完全にビジネスと割り切ってほしくない分野であることもたしかです。そこで公の監視下、より高いサービスを安心して受けられるようになるのが理想です。そのためには、自分の収入に見合った施設があることや、「保護者にも自分と子どものためにどの施設を選ぶのか」という非常に難しいハードルを越える気概を持つことが要求されてくるのではないでしょうか。しかし、これは現在のような待機児童が過剰の場合、なかなか難しいのが現状ですので、供給が追いついた場合のこと。
既存施設の改修財源の確保を!(tomy13)
公設民営賛成です。民営にすることで保育を受ける機会が増えるのであれば、公営にこだわることはないと思います。ただ、そのための条件整備は慎重にしなければ、ベビーホテルのような事件が起こることは免れないでしょうし、営利が先に立っては誰のための保育か見失うことになってしまうのではないでしょうか? また、新しい施設を別用途施設の改修でつくることは新しい視点だと思いますが、既存の保育施設の有効利用も積極的に検討していく内容だと思います。
保育ノウハウなどのソフトのストックは、一朝一夕にはできないものでしょう。わたしは建築設計の仕事をしているので、保育園の増改修工事の設計をする機会があるのですが、「規制緩和で園児の定員増員を認められても、その施設整備のための財源がない」という現場の声をよく聞きます。一時保育事業や病児保育事業などが認可されても、増築の資源がないので、遊戯室の一角や保母休憩室を利用して保育しているのが現状のようです。また公設民営の場合、運用後の施設管理の所在が「公」のままだと、老朽化や制度の変動に対するリニューアルに柔軟に対応できないという危惧があります。以上のような懸案点もありますが、保育を受ける機会が広がるという点で、基本的には公設民営に賛成です。
公立保育園の民営化についてのネックポイントは(園長)
利用者のニーズに合った保育所を望むならば、また税金の無駄遣いを是正するならば、保育園を民営化すべきです。でもいま、公立保育園にいる職員の処遇を考えれば、民営化は非現実的なものになります。2対1での保育とありましたが、これは決して、利用者のためを思ってやっていることではありません。職員組合との協定で、国基準の3対1にできないのです。だから、公立保育園は、定員まで子どもを入れることができません。乳児保育や延長保育もしかり。楽をしてきた公立の職員にとって、民間保育園のような、忙しいけど活気のある生き生きとした保育利用者のニーズに、常に弾力的に応えてゆく保育はちょっと無理かな。
公立を民営化するとなっても、職員ごと民営化はできないのです。保育コストを考えれば、民営化は必須です。職員の問題さえ片付けば。
|

|
|


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について