ホーム > news &policies > 規制改革メルマガ > vol.1
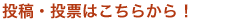
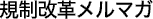
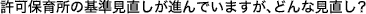
2001年7月20日(金)
今回のご意見テーマ
「待機児童をゼロにするために、現状、国の基準よりも質の高い(ある意味で厳しい)保育所設置の基準を設けている地方自治体も、国の基準に従うべきでしょうか?」
たくさんのご意見ありがとうございました。掲載させていただいたご意見のほかにも、「保育園と幼稚園の統合」「調理室は保育所に不可欠」「保育所の税控除」など、広範囲なテーマについての意見をいただきました。今後のテーマにさせていただきます。
さて、この場を借りて、読者のみなさんにお願いがあります。
「ewoman:規制改革メルマガ」は、単なる情報提供や意見募集にとどまらず、具体的な政策提案にまで反映させることを目標としており、わたしが出席している総合規制改革会議で行われている議論の争点を、リアルタイムで扱っていきます。つまり、どのような言葉を政策提案に盛り込むのか、につながるようにわたしの質問は毎回設定されています。そこで、みなさんには、毎週わたしが投げかける問い(「今回のご意見テーマ」)になるべく具体的にお答えいただきたいのです。まずはじめに、イエス(賛成)、ノー(反対)と書いてから、ご意見をお書きください。また下記の、ほかのメンバーの投稿を読んでのご意見も受け付けています。建設的に、意見を積み重ねていきましょう。
みなさんの知恵を集めた政策提案ができるよう、今後ともどうぞよろしくお願いします。
ewoman:規制改革メルマガ編集長
佐々木かをり
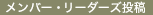

地方自治体の基準はそのままでいい(crazydog)
子どもを預ける際には基準の厳しいところで質を求めてきた。納得した上で預けたから仕事が続けられた。子どもの待機はゼロにしなければならないけど、高い基準はそのままでもいい。その代わり無認可と言われているところに、最低の基準が設けられたらいいのではないか。次回のテーマになっているかもしれないけど。
子どもには空間が必要であり、砂場や土も必要、それをどのように確保していくか。ただ預かる、預けるのではなく、人としてどのように成長させるかが大事な選択なのでは?
地方の特色を生かして(ななこ)
すべて国で一律に決めつけるのは反対です。これから進めて行かなくてはいけない地方分権にも逆行します。それぞれの地方で保育事情にも差があるはずです。
一つの基準に当てはめると無理が出てくるのではないでしょうか。質を落とすということは、子どもにとっては不利益になります。基準以上のものをわざわざ下げる必要はないと思います。
チェック機能が大事なのでは(けこ)
まだ子どもはいませんが、今すぐにでも欲しいと思ってます。そのときも仕事は続けたいので、保育所に関してはとても興味があります。 わたしが一番いいと思うのは、
- (国が定める)統一最低基準を作る
- 認可/無認可を問わずこの最低基準はクリアしなければならない
- 個々の園が付加できるサービス(延長保育etc.)に対し行政は介入しない。すなわち利用者(親・子)にとって望ましいサービスの導入を制限してしまうような規制は設けない
- 行政は地域の実情にあったサービスが付加できる柔軟性を持つ
- 民間に委託するなどで各園の実情、基準のクリアが守られているかをチェックする
- チェック機能は付加サービスの適切な価格設定にも反映される
最低基準をはるかに超える、よいサービスを提供する公立園は、他の園より若干価格が高くなってもいいと思う。
保育所を利用する親・子どものニーズはとても多様だと思うんです。比較的短い利用時間だが、内容を濃くしてほしいとか、どうしても平日は長時間預かってもらわなければならない、不規則な勤務時間に合わせたい...など。今の保育園って画一すぎるような気がするんです。特に公立は。公立がまかなえない部分を私立、無認可がカバーしている。必要な人が多いから「ちびっこ園」みたいなことが起きてしまう。公立・私立、認可・無認可といった枠を超えて、多様なニーズに対応できるいろんなタイプの保育園があってもいいんじゃないでしょうか? 少人数で年齢を区切った子どもだけを預かる保育園とか。
量より質は当然です。(miechan69)
今回の話題では、単純な保育人数について書かれていますが、わたしが常々考えているのは、預かってくださる保育士の質にも注目して頂きたい、ということです。私見ですが、免許が簡単に取れすぎるのではないかって思います。教職課程を受け、教育実習をし、試験が受かればOKという単純なもので本当にいいのかなと思います。また、教職から何年も離れた場合は、更新できないなどの規制ってあるのでしょうか? そういう点についても改革を進めていこうという状況はあるのか、教えて下さい。
地域の独自性は尊重すべき(tarsh)
近々、ワーキングマザーになる事を検討している者です。規制緩和が叫ばれている中で、画一的な規則に必ず従え、というのはナンセンスとしか言いようがありません。自身、厚生労働省の法律を仕事で読む機会が多いのですが、広く実状を知った上で作成している法律とは思えない点が多々あります。
待機児童をなくすためには、まず保育所の数を増やすことです。適切な構造改革及び省内リストラ(首を切れとは思ってません。役所が民間企業と同じだけの経費節減をすれば赤字が減るどころか、お釣りがくると思っているので)を行えば、保育所の増設、雇用の増大にもつながる保育士の増員は可能です。
今回のテーマに対する意見は、最低基準を設定し、それを超える部分については公営・民営を問わず、それぞれの企業努力とするべきと思います。そのほか、病児の保育園、障害を持つ子どもの受け入れについても取り上げてほしい。
幼児教育も認可して(あゆむ)
うちの息子が通う幼児教室は、30年の歴史ある無認可の教室です。2歳児〜5歳児がいます。泥んこ遊び、海遊び、季節を感じさせる外遊び、大きな幼稚園では体験できないことをさせてくれます。しかしながら財政的に苦しく、認可と無認可では補助金などかなり不公平です(公立の保育園児と無認可の教室では園児1人当たりに使われている税金額が全然違う!)。
いま、間借りしている公務員住宅の集会所の建物の建て壊し問題もあり、存続が危ぶまれており、たいへん残念です。小学校の空き教室など使えればいいのですが却下されます。2歳児などの保育もしているので、基準を満たしている教室なら認可してほしいものです。待機児削減に貢献できるのに!! 今回のテーマに関しては、質の高いところが国の基準に従う必要はないと思います。園の差別化ができ、ニーズに合った所をそれぞれが選べばよいと思うので。

従うべきだと思います。(えむ・えむ)
現在、区の保育園に2歳の子どもを預けています。20人の子どもに対し、正規の保育士は3人で、あとはパートなどの方が補助しています。人数的には、十分です。
保育園では、自分のクラス以外でも、園長先生やほかのクラスの先生が子どもの名前を覚えてくれていて、園全体で見てくれているように思います。待機児童が多い現状で、国の基準以上の待遇は考え直した方がよいのでは? でも、ホールを教室に…など、そこまではしてほしくないというのが正直、保育園に通わせている親の気持ちです。待っている方には申し訳ないと思いますが。
数年前、上の子を2回ほど無認可の園(今問題になっている園です)に預けたことがあります。初めてだったこともあるのでしょうが、よい印象がなくそれ以来利用しませんでした。無認可の園がすべて問題があるとは思っていません。認可、無認可という区分ではなく、子どもを安心して預けられる環境か、そうじゃないかを明確に知りたいと思います(たとえば、多少狭くても保育士が十分な数そろっているとか。すべての条件が揃わなくても、安心して預けられるところはきっとあると思うので)。
|

|
|


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について